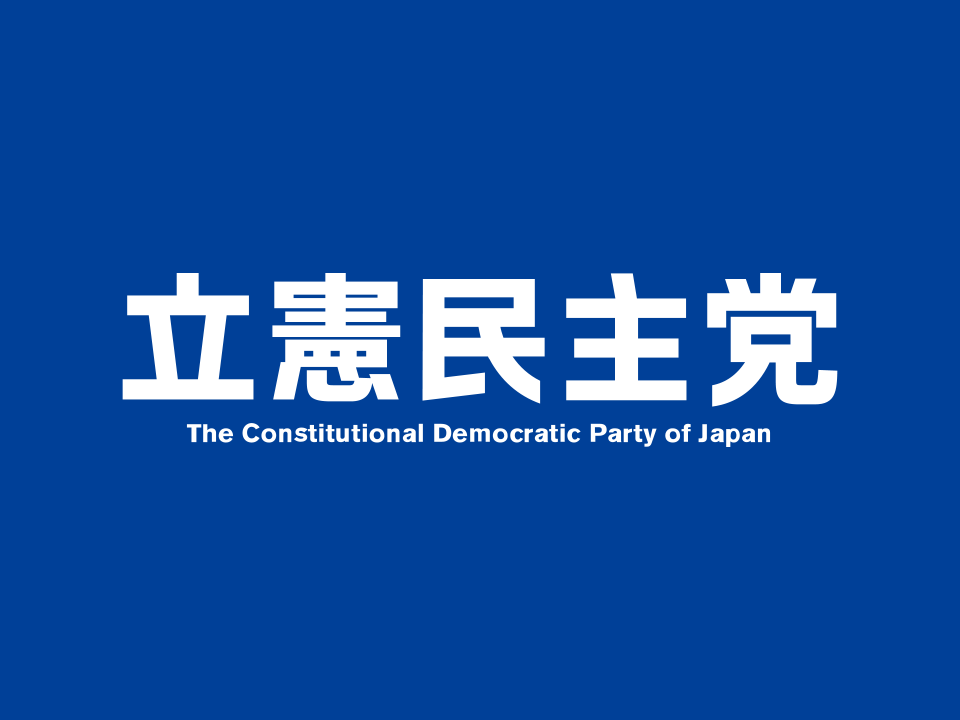2024(令和6)年6月20日
「次の内閣」閣議
立憲民主党の島政策(中間報告)
島政策プロジェクト・チーム
1.国土連続性の確保(離島航路・離島航空路の低料金化)
2.物価の格差是正(税制上の措置やガソリン価格の値下げ)
3.生業の確保と生活の利便性の向上(スマートアイランドの推進等)
4.医療体制の確保
5.教育環境の確保
離島は、我が国の領土・領海・領空、排他的経済水域等の保全といった国家的役割や、自然との触れ合いの場の提供、食料の安定供給等の国民的役割など、重要な役割を担っています。 離島振興法は、離島の本土との隔絶性に起因する生活環境等の後進性の排除や島民生活の向上等を目的として、1953(昭和28)年に議員立法により10 年間の時限措置として制定されました。以降、10 年ごとに議員立法により改正され、同法に基づき、ハード整備支援に加え、ソフト対策支援の充実も図られてきました。
しかしながら離島は、今なお急速な人口減少により過疎高齢化が進み続けています。限界集落となり存続の危機を迎えている島が多数存在しており、これまでどおりの離島振興策を続けていても、島の人口減少を食い止められません。また、離島は本土に比べ物価が1割以上高く、地域格差の是正等の課題があります。さらに、昨今の世界的な原油高は、離島の日常生活に深刻な影響を及ぼしています。
そのような状況の中、これからも離島が国家的役割・国民的役割を担い続けるには、島で暮らす全ての人に届く新たな公共政策が必要です。立憲民主党は、以下の政策を実現するための具体的な検討を進めます。
1.国土連続性の確保(離島航路・離島航空路の低料金化)
国民の生活を支える最も基礎的な社会資本は道路であり、離島の住民にとって航路は「海の国道」として生活に不可欠です。また、航空路も同じく国道のようなものです。
一方で、これらが陸上交通に比べ割高な運賃水準であることが、地域間格差の是正や離島への定住促進の妨げとなっています。
このため、離島の隔絶性に起因するこのような条件不利性を解消し、一体性を確保する「国土連続性」を離島政策の柱とし、これを担保する手段として、離島航路や離島航空路の運賃低廉化に取り組みます。
現在、「有人国境離島法」に基づく有人国境離島で実質的に離島住民・準島民に限定して実施されている航路及び航空路の運賃割引(フェリー=JR在来線並、ジェットフォイル=JR特急指定席並、飛行機=新幹線並)は、島民の負担軽減から評価できるものの、島民の島外での消費を促してしまう懸念があることから、2024(令和6)年4 月に同法を改正する「有人国境離島法改正案」(国境離島みんながJR運賃並法案)を提出しました。同法案は、旅行者や、島外から日常的に業務等で島内へ通う方など、全ての人を運賃割引の対象としようとするもので、交流人口を増加させることによって島内の消費を伸ばし、離島経済の活性化を図ることを目指しています。この際、国の負担率を大幅に引き上げることで、離島自治体の負担が増えないように配慮します。
また、有人国境離島法の対象ではない離島振興法の指定離島については、低廉化のための国からの補助が、唯一かつ赤字の航路における離島住民を対象とした割引(地方バス運賃並)といった地域公共交通確保維持改善事業によるものに限られ、その実施状況も2023(令和5)年度で12 航路3航空路線に留まります。全国の離島一般に、有人国境離島で実現を目指している運賃割引が導入できるよう、「国土連続性交付金」を新たに創設すること等を含めた制度を検討し、その実現に取り組みます。
さらに、老朽化が進行しながら船価が高額なために更新が進まないジェットフォイルの建造を支援するなど、船舶や航空機に対し必要な設備投資を行うとともに、架橋整備についても積極的に取り組みます。この際、地域の実情に配慮し、架橋事業後も継続して振興を図るという発想のもと、2022(令和4)年の離島振興法改正の際の決議を踏まえ見直された架橋に伴う指定解除の基準について、指定が継続されるよう離島住民の経済的負担等を考慮する基準への更なる見直しを求めていきます。
2.物価の格差是正(税制上の措置やガソリン価格の値下げ)
離島は、海上輸送費の発生や販売規模などの要因から物価が本土に比べて1割から3割程度高い傾向にあり、物価の地域間格差の是正が課題です。
そこで、離島振興法第19 条に「離島振興対策実施地域の振興に必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする」とあることを踏まえ、本土との格差是正を図る観点から、離島の税制上の措置について検討します。
例えばコルシカ島(フランス)では、島内の相対的物価高を抑制するため付加価値税等の税率を本土よりも低く設定するという施策が講じられていますが、こういった諸外国の例も研究し、島内消費の拡大や、離島で暮らす全ての人の所得が向上する島内循環型の経済を構築して、離島の若者の雇用を創出します。
また、昨今の世界的な原油高も加わり、ガソリン価格が2024(令和6)年5 月時点で、長崎県の壱岐では1ℓ200 円、上五島では208 円、鹿児島県の離島平均では198 円まで値上がりしており、「もう生活できない」との声が多数寄せられています。民主党政権時代に創設されたガソリン価格を値下げするための補助金(現在は7円~70 円)が予算化されており、2022(令和4)年の離島振興法改正の際の決議においては、ガソリン小売価格を引き下げることとされました。一方で、本土との格差の十分な解消は道半ばであり、公共交通機関が脆弱な島での暮らしを支えるために更なる財政出動が必要です。
このため、現行の予算措置を法制化することで恒久的な扱いとし、補助金の額を増額することで、島民の暮らしを支えます。
3.生業の確保と生活の利便性の向上(スマートアイランドの推進等)
若者が島に残ることのできる生業の確保や、島で暮らす全ての人の生活の利便性の向上を進めます。このため、離島地域が抱える産業振興、交通・物流、医療・介護、エネルギー等の課題の解決に資する新技術を積極的に活用するスマートアイランドを推進し、離島地域の活性化を図ります。
離島の基幹産業である農林水産業は、その生産額が1990(平成2)年のピーク時の半分以下に低下しており、ICTの活用を含む先端技術の導入による生産性や付加価値の向上を推進します。
従来からの島の生業の高度化に加え、島での起業や、島に外部から仕事を持ち込むサテライトオフィス化を進め、定住のための生業を確保します。デジタルツールの活用が進み、働く場所を自由に選べるようになっていることに加え、自然環境豊かな地方への移住にも関心が高まっており、このような需要を取り込み、自然環境を保全及び活用しつつ、島でのテレワーク等を推進し、移住者を増やします。
また、小規模な離島をはじめとして島民の生活を支える物流網の維持に懸念が生じており、ドローンを活用した物流を拡大するとともに、貨物船の船舶建造や運行支援等についての新たな措置を検討するなど、生活物資を含む離島の物流コストを削減し、将来にわたる物流網の確保を図ります。
さらに、島の交通弱者や観光客の移動手段として、グリーンスローモビリティを推進します。高齢化の進展に伴い介護サービスの必要性が更に高まっていくことが見込まれることから、介護ロボット導入により、人材不足解消を進めます。
生業や生活を支え、新技術の活用を進めるためのインフラとして、情報通信ネットワークを整備するとともに、島の恵まれた自然環境を活かした再生可能エネルギーの地産地消を進めます。
4.医療体制の確保
医療提供体制の確保は島民が離島で安心して生活していく上で必要不可欠であり、島に医師が不在であっても医療とつなぐことのできる「オンライン診療」の活用を進めます。その際、現地の看護師ができる医療行為の範囲を広げる特別資格の付与や、島の医療関係者による処方箋の発行が可能になるような制度を創設します。
また、「島限定特別看護師」に対し、特定行為に関するスキルを磨くための研修を行うとともに、十分な報酬が与えられる魅力的な職業とし、意欲のある優秀な人材を島へ呼び込みます。
島のハンデを克服するため、離島医療センターの設置や医薬品運搬への ドローンの活用などを積極的に進めるとともに、港湾に接岸可能な小型の診療船を整備し、看護師等の人員設置基準を緩和します。
5.教育環境の確保
離島は「地域をフィールドにした課題発見・解決活動」を行う教育環境に適しています。都会の大規模校にない強みである「個に応じた学び」や、「自己肯定感が高まる」教育改革を具現化する学校として位置づけ、都道府県の枠をこえた「離島学校組合」を設立します。
教職員を好待遇で迎えて教育の質を高めます。また、島の学校を存続しやすくするため、その教職員数の拡充を図るとともに、島における特別支援教育を充実します。さらに、小規模な学校の維持や活性化にも寄与する離島留学に対する補助を拡大します。
オンライン授業の普及を活かし、島の高校生と社会人、島と島を繋ぐような新たなプロジェクトを推進し、教育の一環として確立させます。