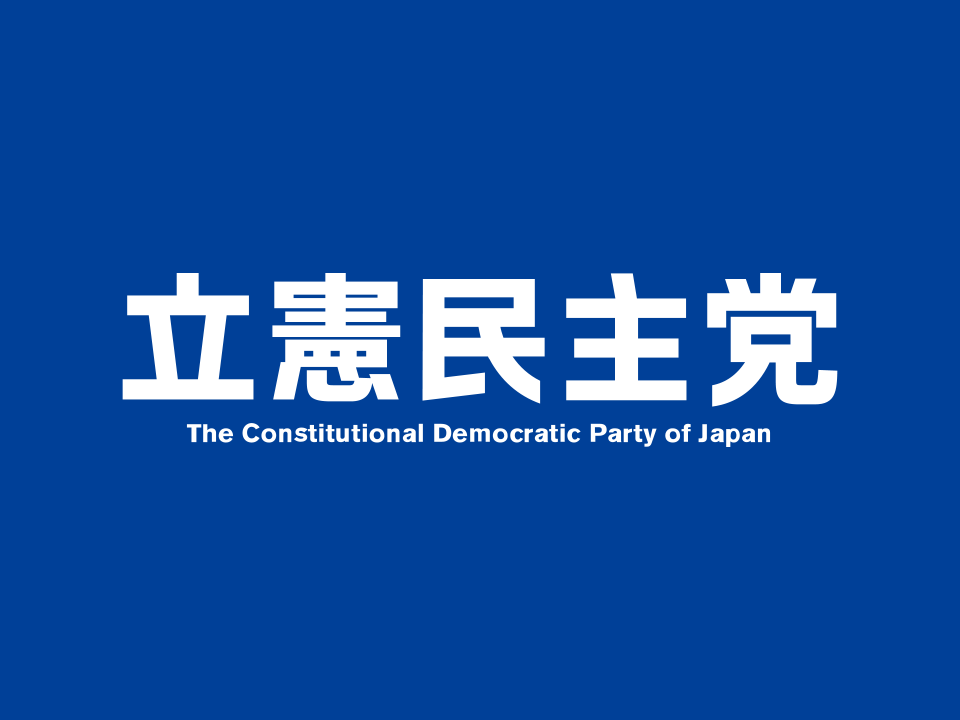ジェンダー・ギャップ指数2024発表にあたって(コメント)
ジェンダー平等推進本部長 西村智奈美
世界経済フォーラム(WEF)が、ジェンダー平等の度合いを示す「ジェンダー・ギャップ指数2024」を公表しました。日本の順位は146カ国中118位で、昨年の125位から7ランク順位を上げました。しかし、引き続き主要7カ国では最下位となっています。
順位が上がった背景には、政治分野における順位が前年の138位から113位に大幅に上がったことがあります。これは女性閣僚が過去最多になったことが反映された結果ですが、一方でジェンダーギャップ指数は0.118に留まっています。指数の指標である衆議院における女性議員の拡大を進めない限り、この数値が大きく改善される見通しは立ちません。
また、経済分野は120位となり、前年の123位からわずかに上昇しましたが、男女間の賃金格差や女性の管理職比率の低さが依然として大きく響いています。厚生労働省が今年1月に公表した男女の賃金格差では全労働者で69.5%、正規雇用労働者で75.2%、非正規雇用労働者80.2%となっており、同一労働同一賃金の具体化の遅れが深刻です。
政府は2005年の男女共同参画基本計画で「2020年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%程度とする」との目標を掲げましたが、2020年にはこれを「2020年代の可能な限り早期」に先送りしました。2018年に制定された「候補者男女機会均等法」は依然理念法に留まり、クオータ制の導入などには至っていません。また、今や経済団体も含めて導入を求めている「選択的夫婦別姓制度」も、自民党の反対により議論が進まないのが現状です。
立憲民主党は2022年の参議院選挙で女性候補者比率、当選者比率とも50%超を実現し、2023年の統一地方自治体選挙では女性議員の議席を60議席拡大しました。そして、来るべき衆議院総選挙では女性議員の拡大に向けて、新人女性候補の積極的擁立に党をあげて取組んでいます。
また、政策面でも非正規雇用者の待遇改善、選択的夫婦別姓の実現、学校におけるジェンダー平等教育や包括的性教育の充実などを通じて、男女の経済的・社会的格差の解消、多様性が認められ誰もが個人として尊重される社会づくり、困難を抱えるあらゆる女性の支援などを進めていきます。
あらゆる分野におけるジェンダー平等の推進は今や世界の潮流です。立憲民主党は、次期総選挙においてジェンダー主流化を政策の柱に掲げ、政権交代を実現し、ジェンダー平等を着実に具体化していきます。