立憲民主党は、2月26日午後、食料・農業・農村政策WT(座長・田名部匡代参院議員)・農林水産部門(部門長・金子恵美ネクスト農林水産大臣・衆院議員)合同会議を国会内で開催、鈴木宣弘東京大学特任教授・名誉教授から「日本型直接支払の実現に向けて」をテーマにお話しを伺い、質疑応答を行いました。次いで、「食料・農業・農村基本計画に盛り込むべき事項について(申し入れ)」の一任結果報告と「高病原性鳥インフルエンザ対策の強化に関する申し入れ(たたき台)」についての協議を行いました。また、議員立法の山村振興法の一部を改正する法律案について、各党協議の状況の報告を行いました(司会:野間健農林水産部門長代理・衆院議員)。
冒頭、田名部WT座長より、「日本型直接支払制度がどうあるべきか、有識者の方々からお話をお聞かせいただいている。日本の農業が危機的状況にある、食料安全保障が脅かされている中にあって、農業の現場を守っていくのか。それは結果として、農家を守るということではなく、国民の命を守るということになる。ぜひ、皆さんと勉強し、制度の構築に向けて進めさせていただきたい」とのあいさつがありました。
次に、金子部門長より、「鈴木先生からご指導いただけることは、本当にありがたいことだと思っている。たぶん、たくさんの厳しいお言葉をいただくと思う。しっかりと学ばせていただき、国の食料安全保障確立のために頑張っていきたい」とのあいさつがありました。
■鈴木宣弘東京大学特任教授・名誉教授から「日本型直接支払の実現に向けて」についてヒアリング
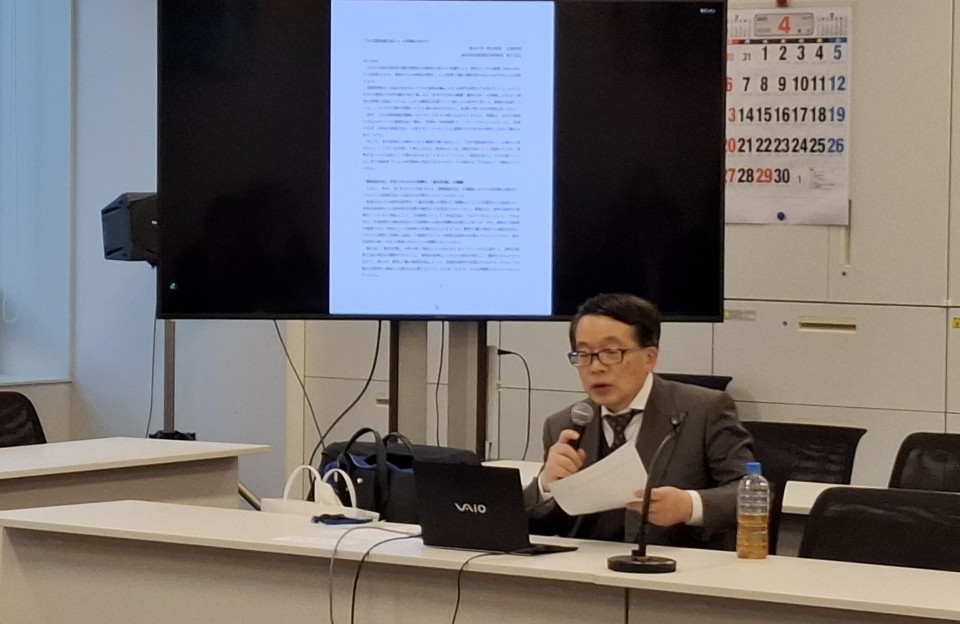
鈴木特任教授からは、「『日本型直接支払い』の実現に向けて」をテーマに講演をいただきました。
開口一番、鈴木特任教授は、「日本型直接支払い実現のネックとなっているのは財政の問題。財政の壁が厚すぎる」と断じました。
また、『日本型直接支払い』と称したのは、欧州型の固定支払とアメリカのような不足払、変動型の支払を合わせて実施する必要があるという意味であると説明しました。
食料自給率について、「基本法改正により食料自給率が重要な指標ではなくなり、食料自給力に係る様々な指標を掲げることとしているが、食料自給力の構成要素がどれだけ確保されているかによって、総合的な自給率が計算される。両者はリンクしていることが理解されていない」という見方を示しました。また、「飼料自給率を考慮した食料自給率は38%であるが、肥料がなく収量が半減すると22%、種子の自給率を10%と想定すると実質自給率は9.2%」という試算を提示しました。
また、2010年、民主党政権で食料・農業・農村政策審議会企画部会長を務め、食料・農業・農村基本計画を取りまとめたときに、食料自給率50%を達成するための財政負担所要額の試算を示したことを紹介し、食料自給率目標達成のための必要予算と工程を示さなければならないとしました。
「農業・農村が疲弊している中、基幹的農業従事者数が減少していくことを前提にして、企業参入やスマート農業や輸出で、一部の人が儲かればいいという議論にしてしまっている」として、「政策が悪いから農業従事者がいなくなっている。そうならないように政策を変えるという議論がない」と批判しました。不測時の食料安全保障について、「平時は支援しないで、有事になれば食料供給困難事態対策法で命令する。疲弊している農家に穀物やサツマイモを強制増産させて強制的に供出させるもの。私は、サツマイモを例にして批判していたが、4月1日から施行される政令で、重点的に要請する農林水産物のリストからサツマイモを消した。そういう話ではない。そういう発想しかない」と重ねて批判しました。
価格転嫁の仕組みについて、「農家のコスト増を強制的に小売価格に反映させることはできない。フランスのエガリム2法もそんな強制力はない。それが分かったため、卸売市場法に努力義務を付け、協議会を作り、コスト指標を作って、みんなで価格転嫁をしようといって、やったふりをしようとする。そのための適当な予算を付けているが無駄。ごまかすための予算だ」と断じました。
2024年11月29日に公表された財政制度等審議会の建議に触れ、「建議では、『農業予算が多すぎる。飼料用米補助をやめよ』という。国家戦略で飼料用米をやると言っていたのに、金額が増えてきたからやめるというもの。大局的見地がない。備蓄米は少なすぎるのにもっと減らせという。極め付きは食料自給率を上げるのに金をかけるのはもったいないから輸入すればよいと。危機意識が全くない」と批判し、「これを打ち破るのは大変だが、頑張っていただきたい」と呼びかけました。石破総理が農相時代に発表したプランと戸別所得補償制度について、「2009年、石破農相(当時)が、私の著書を熟読され、『米の生産調整をやめていく。そうすると、米価が下がるので農家の努力で何とかなる米価と市場価格の差額を補填すれば、生産者・消費者の双方を支え、食料安保が確立できる。必要経費は3,500億円から4,000億円』という考え方を示した。これは、明らかに、民主党の戸別所得補償制度を意識した政策。その1か月後には、民主党政権になったが、事務方が石破プランに基づき、準備を始めていたので、戸別所得補償制度の実施に引き継がれた」と説明しました。
戸別所得補償に対するバラマキ批判に対しては「平均生産費13,700円が最低限補償される仕組みとなっていたが、全農家をカバーするものではない。2万円補填するといえばバラマキと言えなくもないが、13,700円以下のコストを実現していれば差額はボーナスとなる。高いコストで生産し、安く売っている人には焼け石に水。標準的な生産コストと標準的な販売価格をどうとるかによって、バラマキにもなるが、規模拡大や経営をよくして頑張る人を延ばす政策にもなる。実際、戸別所得補償制度は、規模拡大の意欲を高めるとして、稲作経営者会議の大規模稲作農家の皆さんにも高く評価されていた」とし、その復活を訴えました。また、鈴木特任教授は、スイスが直接支払体系を組み替えて、直接支払の3分の1は供給補償支払いという農地面積当たりの支払いを増やした上で、景観、環境などに応じた支払いを追加していくという仕組みとしたことを紹介し、これを参考に「食料安全保障確立基礎支払」を創設することとし、超党派の議員立法による食料安全保障推進法(仮称)の可能性を提起しました。
戸別所得補償というと農家だけを助けるというイメージが強すぎるので、名称を食料安全保障確立基礎支払とするなど、国民全体のための政策だということを示す必要があるとしました。仕組みは、農地面積当たりの基礎支払い、畜産の場合は家畜単位当たりの基礎支払を行い、様々な条件による加算、生産費が上がったり、価格が低下したりしたときの加算を組み込むとしました。
さらに、備蓄在庫を積み増し、今回のような米不足やバター不足に際して、需給の最終調整弁として、政府が責任を持ち、備蓄食料を人道支援に活用するという仕組みを整備するとしました。
鈴木特任教授は、「食料安全保障推進法について、ほぼ全政党にお話し、自民党議員からも賛同をいただいたが、裏金問題の噴出で議論が止まってしまった」とし、「立憲民主党がもともとやっておられた政策。国民民主党からは党の看板政策に使わせてほしいとの話があった。総選挙の結果、立憲民主党の議席数が増え、与野党伯仲となった今こそ、この政策を導入するチャンスである」と期待をにじませました。
その上で、「農地面積当たりの交付単価について、10a当たり3万円、せめて1万5千円と考えていたところ、水田活用の直接支払交付金を広く薄く伸ばして、10a当たり2千円とするという話を仄聞した。これでは何にもならず、こうした議論で収めないでいただきたい」として、「立憲民主党が主導権を発揮して、財政の壁を打破していただけないか」と結びました。
■質疑応答
参加議員からは様々な質問がありました。
生産調整について、「米の需要が毎年10万トン減っているということで生産を減らす生産調整をしてきているが、一方、生産調整を止め、作るか作らないかは農家の経営判断とするという考え方もある。需要が下げ止まることもあり、米騒動前は米には割安であった。減らすだけが生産調整の目的ではない。増産について、どのように考えるか」(小山展弘衆院議員)との質問がありました。
これに対し、鈴木特任教授から「基本的には同じようなイメージ。米の消費が減っているといっても、備蓄が1.5か月分しかない。少なすぎる。小麦の輸入が止まれば米でパンや麺を作る。とうもろこしが入らなければ餌米。貧困家庭が増えているので、こども食堂やフードバンクを通じた援助物資として政府が米を買って届ける仕組みなど、食料安全保障上の備蓄需要を考えれば、拡大できる。状況を見ながら増産してもらい、備蓄やいろんな用途に仕向け、そこに財政出動すべき。精米歩留まり率が下がっているので、作況指数だけみると減らしすぎてしまう。341円の関税を超えて米が入ってきて、米の自給率が下がり、いざというとき、食べられないということになりかねない。価格の暴落を考え、状況をみながら増産に舵を切ることも必要。増産すれば価格が下がる可能性があるので、主食用米に対する補填がない状況ではやめる人が増えてしまう。補填を入れることを前提に、増産できる仕組みを作っていただけ
れば」との回答がありました。
令和の米騒動について、「悪徳業者が買い占めているという話もあるが、米不足の原因は何か。明らかに需給ギャップで米不足が起こっていると思っているが、対策は買戻し条件付きの政府備蓄米の放出。1年以内に買い戻すと言ってしまえば、結局、供給量は減る。米の価格を安定させることができるのか。国民が安定して米にアクセスできるようにするための備蓄米の運用はどうあるべきか」(山田勝彦衆院議員)との質問がありました。
鈴木特任教授からは、「政府は、米は足りている、自分たちがやってきたことは間違っていない、悪いのは流通だと言っているが間違っている。米の不足感があるから、業者はビジネスチャンスとして、そういう行動をとる。悪いのは流通ではなく、流通がそういうふうに動く、不足状況を作った政策。政策を変えない限り何も変わらない。政府備蓄米の放出には米価を下げる効果はない。実際、取引価格は上がっている。備蓄運用については、賛否があると思うが、米価が2万円を超えたら放出し、1万5千円に下がったら買い入れ、一定の価格帯に落ち着くように誘導する仕組みを決めておけば、それを見て、市場は行動し、米価はその範囲に収まるような状況になる。生産者が苦しい状況になるのであれば、補填措置を準備しておけばよい。市場には介入しないというのが基本的な流れになっているので、賛同が得られにくいかもしれないが。また、今の米価は、30年前、40年前の米価である。5キロ4千円で大騒ぎしているが、1990年の5キロの小売価格は4,900円だった。それからいかに下がってきたかと
いうことだ。ただ、消費者も貧しくなってきているので、今の負担は厳しい。生産者の適正価格と消費者の適正価格が乖離するので、そこを埋める直接支払が必要」との回答がありました。
これに関連し、参加議員から、「収益の低い米は誰も作ろうとしない。土光臨調のときに叶芳和氏が10ha規模の農家が50万戸いればたくさんだと言ったことがあるが、現状はそれよりも下回っている。団塊の世代は昔の価値観を持っているので、金にならなくても作るが、団塊ジュニアは絶対作らない。この危機感を共有すべき。全面的に財政で支えるしかない」(篠原孝衆院議員)との発言がありました。
鈴木特任教授の講演の中で、農地面積当たりの交付金単価を2,000円とする考え方があるとの指摘があったことについて、田名部匡代WT座長より、「われわれの案ではない。雑談の中で出てきた数字で、これに環境払とか中山間払いとかを加算していくのか、それとも、所得補償の仕組みとするのか。食料安全保障に資する多面的機能をしっかりと維持していくためにどのような制度にするかという話であり、そんなシャビーな議論はしていない。今日の先生のお話を参考にさせていただきながら、制度設計をしていきたい」との発言がありました。
農業従事者数について、「今回の基本計画で、農業者の確保の目標を見送りということになりそうだということが報道されている。かつて、食料自給率目標達成に向けて試算をしたとのことであるが、必要となる農業者数も試算されたのか」(金子恵美衆院議員)との質問があり、鈴木特任教授から、「当時どのような試算をして数字がでてきたかについては私も十分に記憶がないが、どのくらいの数、規模の農家が、適正な生産の維持、コミュニティの維持に必要かという議論をしないといけない。簡単にはやりづらい面があると思う。どういう議論だったのか、確認してみたい」との回答がありました。
農業者以外の消費者も巻き込んだ農地を守る取組への支援について、「農業者と消費者との分断を生んではいけない。食料安全保障を考えたとき、農家だけでなく、農地を農地として利用していることに対して、家庭菜園も含め、ちゃんと作ってくれれば支援し、みんなで農地を守っていくことが必要と思っており、日本版ダーチャ(菜園付きセカンドハウス)をやるべきという人もいる。これまでと違う多くの方々に理解を得られる直接支払の在り方はどうしたらいいか」(徳永エリ参院議員)との質問がありました。
鈴木特任教授より、「自分で農業やりたいという消費者が増えている。そういう方々と一緒にやろうということで、直接支払の理解を得ることは重要。私は、『飢えるか?植えるか?運動』と言っているが、飢えないように植えましょうと。そういうイメージで、みんなでやろうじゃないかと。農家だけでなくて自分たちも分担してやっていくような仕組みづくりをして、ローカル需給圏のような、そこでできたものをそこで消費しましょうという支え合うネットワークづくりを広める必要があると思う」との回答がありました。
食料安全保障の観点からの食料自給率について、「純国産の資材を用いて生産した場合の食料自給率を計算すべきと思うが、この食料自給率を何パーセントに引き上げれば、有事があったときに国民が飢えないと考えられるか、教えてほしい」(神津たけし衆院議員)との質問がありました。
鈴木特任教授から「重要な指摘。いろんな生産要素を組み込んで自給率を示すべきということはぜひ行っていただきたいと思う。どのくらいあればというのは、なかなか難しい問題。実現できるかという問題もある。平成18年の農水省の食料自給率レポートで米や和食を中心とした食生活を取り入れると食料自給率は63%になるという試算が出ている。これが一つの目安。ただし、このレポートは入手できなくなっている」との回答がありました。
関連して、参加議員から「昨年、坂本農林水産大臣が、『和食の献立とした場合の食料自給率は66%』と答弁していた」(小山展弘衆院議員)との発言がありました。鈴木特任教授から「小麦を米でどれだけ置き換えられるか。餌をどれだけ米にできるか。米を活用すれば自給率は改善できると思う。その試算はやってみる必要がある」との指摘がありました。
■報告・協議事項
「食料・農業・農村基本計画に盛り込むべき事項について(申し入れ)」について、金子部門長より、「次の内閣(NC)で一任を取り付けた。微調整する可能性があるが、28日の15時から江藤農林水産大臣へ申し入れる」との報告がありました。
「高病原性鳥インフルエンザ対策の強化に関する申し入れ(たたき台)」について、金子部門長より、「小川淳也高病原性鳥インフルエンザ等対策本部長から農林水産大臣に申し入れることになるが、政策については農林水産部門で議論することになったので、たたき台を作らせていただいた。これは、17日に千葉県知事と面談し、聞き取りをした内容を盛り込んだものである」との説明がありました。
参加議員から「鳥インフルエンザウイルスに耐性を有する鶏について研究を深めるべき旨の項目を追加してはどうか」(野間健衆院議員)との意見が出され、この意見を含め、部門長に一任することを了承、明日の次の内閣(NC)にかけることとなりました。
山村振興法の一部を改正する法律案について、渡辺創副部門長より「先週金曜日、仮の各党協議会が開催され、我が党から提出した意見はほぼ満額回答となった。提出に向けての手続きを進めていきたい」との報告がありました。
