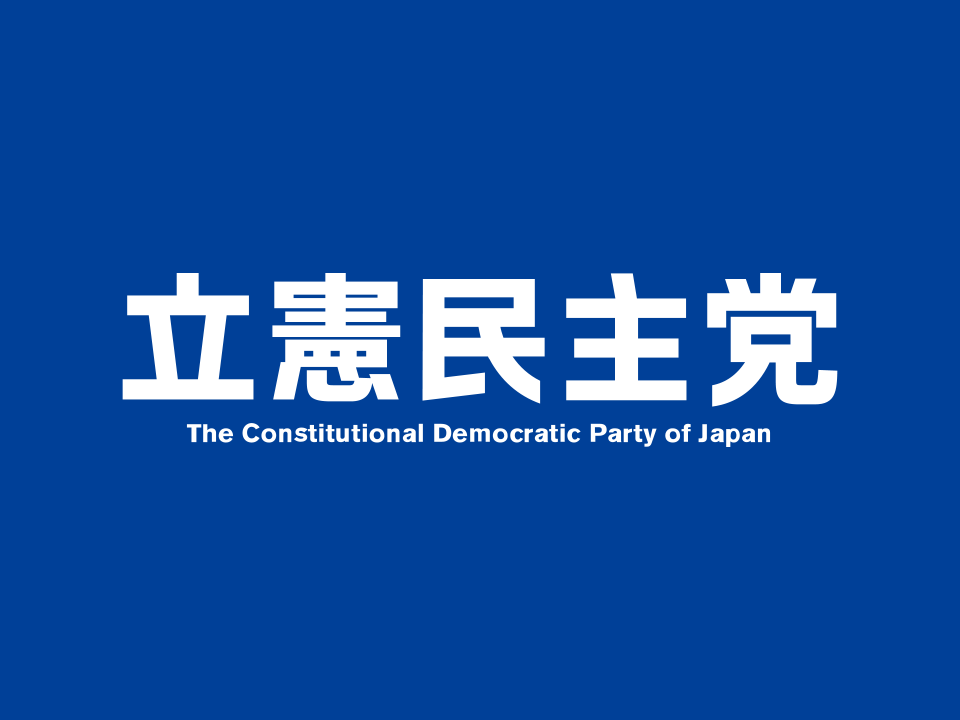地球温暖化対策計画及び第7次エネルギー基本計画の閣議決定について(談話)
立憲民主党
環境部門
経済産業部門
政府は2025年2月18日、「地球温暖化対策計画」及び「第7次エネルギー基本計画」を閣議決定した。気候変動対策は、現在の社会のあり方に影響を与えるだけではなく、将来世代の生活にも大きな影響を与える人類共通の課題である。しかし政府は、充分な国民的議論、国会での議論を踏まず、パブリックコメントの結果の公表とほぼ同時に閣議決定し、2035年の日本の温室効果ガス削減目標(NDC)を2013年比60%と決定した。
現時点においても、気候変動の影響はこれまでにない厳しい気象現象や自然環境へのダメージなどの形で顕在化しており、将来世代への責任を果たすためにも、今取り得る施策を可能な限り実施すべきである。2035年の温室効果ガス削減目標については、国際社会が求める1.5度目標に整合する目標設定が必須であり、IPCCが示す科学的知見などを踏まえ、世界平均で2019年比60%の削減が求められている。政府が基準としている2013年比に置き換えれば66%に相当することから、日本は2013年比66%以上の削減目標を設定するべきである。
また、日本においては、AIやデータセンターの普及拡大等により電力需要の拡大が見込まれるものの、建物断熱や熱の有効利用、省エネ機器の導入など、現在ある技術を活用してさらなる省エネが可能である。エネルギーの使用そのものを減らす省エネルギーをさらに徹底するとともに、地域の資源を活かしてエネルギーを生産すれば、地域に仕事・雇用が生まれ、エネルギー安全保障、地域のレジリエンス向上にもつながる。第6次エネルギー基本計画に引き続き、再生可能エネルギー最優先の原則を維持し、屋根置き太陽光や営農型太陽光発電、洋上風力、地熱、小水力、地中熱などの再生可能エネルギー導入を加速化するため現行制度を検証し、障害となっている制度の見直しや、蓄電池や揚水発電などの蓄電設備の充実を図るべきである。さらに、化石燃料に依存しない社会実現のため、脱炭素の対応が出来ていない石炭火力発電の可能な限り早期の段階的廃止に向けた道筋を明確にするとともに、「原子力発電依存度の可能な限りの低減」の方針は、第6次エネルギー基本計画に引き続いて維持するべきである。
合わせて、脱炭素化の影響を受ける労働者や地域が取り残されることがないよう、公正な移行を実現し、エネルギー多消費産業などに対する脱炭素化支援をより強力に行うことが重要である。
立憲民主党は、より野心的な温室効果ガス削減目標の策定を求めるとともに、1.5度目標の着実な達成と経済成長の両立の実現を目指す。
【立憲民主党】地球温暖化対策計画及び第7次エネルギー基本計画の閣議決定について(談話).pdf