立憲民主党・農林水産キャラバン隊(隊長・田名部匡代参院幹事長)は3月8日から9日、宮崎県の西臼杵郡日之影町、児湯郡高鍋町、宮崎市を訪れました。
今回のキャラバンには、野田佳彦代表、隊長の田名部匡代参院幹事長(農林漁業再生本部本部長)、野間健衆院議員(農林水産部門長代理)、神谷裕衆院議員(農林水産副部門長)、渡辺創衆院議員(農林水産副部門長)のほか、岩切達哉宮崎県議会議員、永山敏郎宮崎県議会議員、松本哲也宮崎県議会議員、山内佳菜子宮崎(参)総支部長・宮崎県議会議員らが参加しました。
一行は、8日に、日之影町の岩田山岳牧場を訪問、山間地放牧を視察、意見交換を行いました。次に、高鍋町の宮崎県立農業大学校を訪問、概況説明を聴取し、意見交換を行いました。続いて、宮崎港の宮崎カーフェリーを訪問、貨物室、客室等を視察したのち、概況説明を聴取し、意見交換を行いました。さらに、宮崎市高岡町にきゅうり農家を訪ね、ハウス栽培の状況を視察したのち、意見交換を行いました。
9日には、JAアズム(宮崎市霧島)にて開催された「立憲宮崎第3回政治塾~立憲民主党の農業政策~」に司会、講師として参加しました。
■岩田山岳牧場にて、山間地放牧を視察、意見交換(日之影町)

一行は、8日朝、日之影町の岩田山岳牧場を訪問し、代表で獣医師の和牛繁殖農家・岩田篤徳さんの案内で、山間地放牧を視察し、岩田さんと意見交換を行いました。
ちょうど、牛舎から牛が出てきたところで、一行は、岩田さんの説明を伺いながら、牛と一緒に放牧地に向かいました。
岩田さんは退職を契機に、牛をのびのびと自由に育てたい、コストを下げたいと考えて、15年かけて、自宅の裏の雑木林や竹林を伐採して、牧草の種を蒔き、牧草地を整備し、放牧を始めたとのことです。現在、約20頭の黒毛和種を山間地にて放牧で育てています。牛20頭の放牧で平均以上の収益を上げることが可能で、労力も節減できると話していました。
放牧地は、永年牧草のセンチピードグラスでおおわれています。センチピードグラスは更新が不要で、湿気や乾燥にも強く、牛の嗜好性も良いという特徴があります。しかし、芽吹きが遅いため、春先から晩秋にかけて青々とした品種に改良することが課題とされています。岩田さんは、その品種改良のための会議に、畜産農家の立場から発言することとしているなど、積極的に活動されています。
岩田さんから、我が国は降水量が多く、単位面積当たりの草の生産量はオーストラリアの何十倍もあるので、少ない面積でも放牧による繁殖経営は十分やっていけるとした上で、耕作放棄地などの遊休地を放牧地として整備し、利用するため、軌道に乗るまでの4~5年間、奨励金を交付するといった支援策があればありがたいとの要望がありました。
■宮崎県立農業大学校を訪問、意見交換(高鍋町)

一行は、高鍋町の宮崎県立農業大学校を訪問、馬場勝校長から農大の概況説明を、次いで、梶原正太郎宮崎県農政水産部農村振興局担い手農地対策課長から宮崎県における農業の担い手確保の取組について説明を聴取した後、意見交換を行いました。
宮崎県立農業大学校の敷地は東京ドーム20個分、90haほど。農業県宮崎における実践農業の教育機関として、将来の県農業を担う人材を育成することを教育方針に掲げています。農大が目指す人材像は、①意欲的にチャレンジする農業経営者、②地域を牽引するリーダーです。
カリキュラムは2年間で、入学して3か月は総合実習として農業・畜産全般を経験し、7月に専攻を決め、各分野に分かれ、専門的な実習を提供しています。先進農家でのインターンシップ、農業現場で必要な各種資格の取得、各種研修会も実施しています。
学科は農学科と畜産学科の2つで、農学科は定員40名。作物専攻、野菜専攻、花専攻、果樹専攻、茶専攻と、農畜両学科から選択可能なフードビジネス専攻があります。
1年前の農学科卒業生の進路は、親元での即就農が7%、農業法人への就職による就農が31%と最多、JAの営農指導員などの農業団体が21%、農業関連産業が14%、その他、公務員や4年制大学への編入もあります。
畜産学科は定員25名。肉用牛専攻、酪農専攻、養豚専攻とフードビジネス専攻の4つの専攻があります。畜産学科の昨年の卒業生の進路は、即就農が25%、法人就農が45%、農業団体が30%となっています。
農大には「アグリカレッジひなた」という模擬会社があります。各学生が1万円ずつ出資し、学生が社長や役員を務め、自ら生産した農産物を会社が仕入れて、即売会などで販売することなどを通じ、会社経営の基礎を学んでいます。
寮は、食費と光熱費は実費となりますが、寮費は無料で、ほとんどの学生は寮に入っています。
農大では、大型特殊免許(農耕用限定)が取得できるほか、農薬散布用ドローン教習施設の認定を受けているため、比較的安価で資格取得が可能となっています。また、農学科では、ASIAGAP(青果物で8品目)等の認証、畜産学科では、JGAP(肉用牛・乳用牛・生乳)の認証を受けています。
入学者数は、長らく定員の65名を下回っていましたが、積極的な募集活動を行った結果、今年度は72名(充足率111%)が入学しています。全国41の農大のうち、定員を上回っているのは4校のみ。72名のうち、9名が県外からの入学者です。また、農家が減少する中、非農家出身の学生が7割を占めています。
昨年度の進路状況は、自営就農16%、雇用就農37%で、自営・雇用を合わせた就農率は53%、農業・食品関係が33%となっています。
今後の取組として、各種情報発信をして、次年度の学生をしっかり確保し、時代に即した教育カリキュラムで学生を育成して進路実現を支援していこうと考えているとのことです。農大の特徴的な取組としては、地元高鍋農業高校と連携した中学生を対象としたオープンキャンパス、前述の模擬会社による経営管理能力の向上、令和6年度からの有機農業のカリキュラムがあげられます。
宮崎県の農業構造を展望すると、平成27年から令和2年の5年間の総農家戸数が約7,400戸減少、1年当たり約1,500戸減少となっており、今後10年間でさらに3割減少すると見込まれています。一方、農業法人は、年々増加しており、宮崎県農業を維持するために、親元就農のみならず、非農家、他産業、UIJターン、定年帰農など多様な農業従事者の確保が必要とされています。
新規就農者は減少傾向にあります。少し前までは年400人確保できていましたが、2年続けて400人を割り込んでいます。令和5年度の新規就農者の就業形態をみると、自営就農が4割、雇用就農が6割となっています。
宮崎県としては、相談から技術習得研修を経て就農準備まで、切れ目なく就農希望者を支えていくこととしています。県内15カ所に、ピーマン、きゅうりなどの施設野菜を中心とした就農トレーニング施設を整備しています。
新規就農者の確保を進める上の課題として、第1に、資材価格の高騰に伴う初期投資負担の増大があげられます。そのため、県として、高齢農業者のリタイヤに伴う中古施設等の円滑な承継やリースの仕組みの構築による初期投資負担の軽減に取り組んでいます。
第2に、定着率の向上があげられます。就農したが、経営がうまくいかない、理想と現実のギャップなどによる離農が、特に、雇用就農において一定程度あります。そのため、研修期間中のきめ細かなフォローアップ、お試し就農として数か月農業法人で働き、現場を知ってもらう取組を進めています。
第3に、宮崎県特有の問題として、品目・地域の偏りがあげられます。台風常襲地帯のため、施設作物での就農が進められていますが、施設野菜では多くの面積を使わないので農地が余ってきます。また、果樹や土地利用型作物の後継者がいないという状況にあります。そのため、作物を問わず技能を習得していく体制を整備していくこととしています。
宮崎県では、農業の経営資源承継支援体制として、出し手農家からの施設、果樹園等の情報を県農業振興公社で一元的に集め、データベース化し、受け手(新規就農者)と出し手(離農希望者等)を地域単位でマッチングさせ、契約締結まで県が伴走方式で支援することとしています。
また、新規就農者は農地の確保のハードルが高く、研修を受けながら自分で農地を探すのは負担が大きいことから、県独自の取組として、あらかじめ就農する農地を決めて置き、県が当該農地を最大3年間、保全管理を行い、その間に技術を身に着け、すぐに就農できるようにしています。就農地の事前確保に対する県の支援は、九州で初の試みということです。
また、令和6年度補正予算での親元就農への国の支援の拡充に合わせ、県として、上乗せして支援することとしています。
入学者数増加に向け、どのような取組を行ったのかとの質問に対し、馬場校長から、「ホームページやフェイスブックは定期的に活用して周知している。また、本校の職員、校長と副校長が手分けして県内の公立・私立全48高校を回って農大の案内をし、進路担当が手分けして募集要項等を持って行って説明をしている。また、高校との連携によるオープンキャンパスを年2回開催している。県内8校ある農業高校の2年生を対象とした1泊2日のアグリドリームキャンプを実施し、体験してもらい、早いうちにファンになってもらうという取組も行っている。こうした地道な手法を積み重ねている」といった説明がありました。
農大卒業生の新規就農者として定着率についての質問に対しては、県課長より、「雇用就農では7割定着で、他産業と比べてあまり違いはない。これは最近の傾向ではないか。一方、自ら経営を開始した人は9割以上の定着率で、こうした人への初期段階における技術面、経営面のフォローには、県として力を入れている」との説明がありました。
パンフレットに記載のあった「チャレンジファーム」とはどのようなものかとの質問に対して、馬場校長より「農大の敷地が広く、もともと飼料畑だった10haの土地の管理が十分できていなかったことを逆手にとり、民間の農業者に3年間お貸しして、機械メーカーとタグを組んで最新の農業を展開していただき、学生にはそれを見せてもらうという取組を実施している。スマート農業という言葉がないことから取り組んでいる」との説明がありました。
卒業後の進路としての雇用就農に向けたマッチングについて、馬場校長より「農業法人でのインターンシップを行うとともに、県内農業法人等約60社と学生とのマッチング会を実施している。マッチング会で感じがつかめれば、1年生であればインターンシップに、2年生であれば採用試験に、という形ができている。マッチング会の農業法人は学生が選ぶ。売り手市場なので、学生は、給与や福利厚生など条件のいいところから話を聞きに行っている」との説明がありました。
また、馬場校長より「入学者のうち、農業高校出身者の比率は7割程度であるが、来年度は普通科高校からの入学者が増える。これは、農大が四年制大学への編入のルートもあると説明したためと考えられる。今年の卒業生にも四年制大学への編入が2名あり、新2年生の1割が四年制大学への編入を希望している。農大でローコストで2年間実務経験を積んでから四年制大学に編入しようというものであるが、農学部に進学し、地元で就農、定着してほしい」との発言がありました。
最後に、田名部隊長は、「教えていただいたことを持ち帰り、党の仲間と共有し、今後の政策に生かしていきたい」と語りました。
農林水産キャラバンが農大を訪問した8日は、卒業式に当たっていました。一行到着時は卒業式終了直後で、卒業生が卒業証書を手に、学び舎を後にしているところでした。若き卒業生たちが、我が国の農業と食を支える担い手として大いに活躍されることを願いつつ、農大を後にしました。
■宮崎カーフェリー株式会社を視察、意見交換(宮崎港)
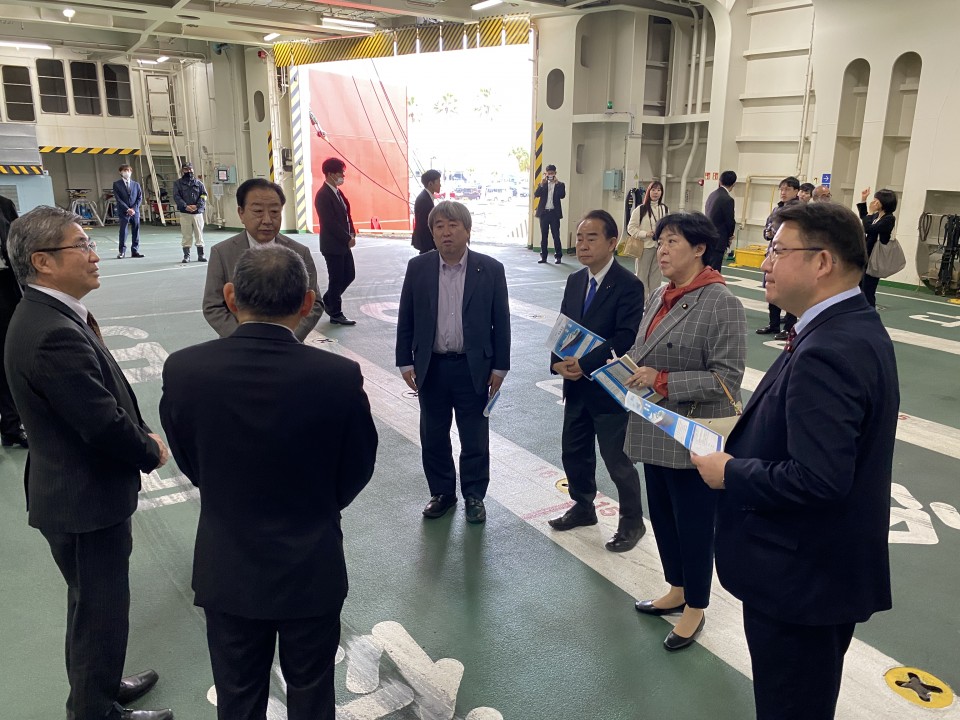
一行は、宮崎港に、宮崎カーフェリー株式会社が所有、運航するフェリーたかちほを視察、郡司行敏同社代表取締役社長から概況説明を聴取し、意見交換を行いました。
同社は、宮崎港と神戸三宮港を2隻のフェリーで運航、フェリーはそれぞれの港を夕刻出航し、早朝に目的地に到着します。
昭和46年、この航路が開設され、変遷がありますが、宮崎の農水産物を大消費地に届ける、全国から旅客を宮崎に誘うという役割を一貫して果たしてきています。
フェリーたかちほは、令和4年3月竣工の新船、旅客船兼自動車渡船で、車両積載台数はトラック163台、乗用車81台、総トン数14,006トン、旅客定員576名、全長194m、型幅27.6m、型深9.6m、満載喫水(型)6.7m、航海速力23.1ノットとなっています。
新船の特徴は、第1に、大型化により、トラックの積載台数を33台分増やしたことが挙げられます。これまでは、ピーク時に乗船できないトラックがかなりありましたが、これを解消しました。また、農産物を運ぶに際して、コールドチェーン、電源は重要で、肉類、野菜類の鮮度保持のため、130台電源を準備しています。
第2に、個室を増やしたことが挙げられます。これまで、トラックドライバーの客室は6人部屋でしたが、個室にし、テレビもみて、ゆっくり休み、下船したら安全運転できるようにしています。
レストランで提供する料理には、宮崎県産の農産物をふんだんに使っているとのことです。
同社の売上げの構成は、トラックが運ぶ貨物が7割、旅客が3割で、貨物については、県内港湾の42%を同社のフェリーが運んでいます。トラックは全体で7万台、その6割が宮崎発、うち7割が、畜肉、ブロイラー、野菜類、養殖魚、ウナギなどの農水産物で、近年は生きた牛も運んでいるとのことです。
輸送量の推移についてみると、旅客については、新型コロナの移動制限による厳しい時期を経て、以前の水準に戻ってきており、貨物については、農水産品、食料であることから、コロナ禍にあっても1万台程度の減少にとどまり、会社を支え、現在は、以前の水準に戻っているとのことでした。
船のセールスポイントとして、1つ目は、平均の出航率97.8%と高水準であること。台風などで欠航することはありますが、非常に高い出航率です。また、車は走行すると事故のリスク、タイヤ摩耗のリスクがありますが、船に乗っている限りはそういうことはありません。
2つ目は、環境負荷の低減。同じ距離を一定のトン数を運んだ場合のCO2排出量は、船舶による輸送では、陸送した場合と比べて83%減少するという試算値があります。
働き方改革法の下、トラックドライバーの時間外労働の上限規制が厳格化された、いわゆる物流2024年問題について、郡司社長から「宮崎から高速道路で30分の休憩を2回はさんで9時間走行した場合、岡山くらいにしか行けない。2人体制で走行する方法もあるが、人件費がかかる。フェリーを使えば、乗船期間中は休息扱いとなる。宮崎から乗って12時間で神戸に到着し、そこから東京まで7時間。関西圏で荷を下ろすこともある。法令を遵守して、無理をせずに東京まで荷物を届けることができる」との説明がありました。
神戸からの貨物について、郡司社長は「上りと下りの貨物は6:4の割合で、神戸からの下りが少ない。神戸からは、飼料、肥料、自動車の部品、新車などが運ばれるが、一般的に、神戸から宮崎に運ぶまとまった貨物はなく、空で帰ってくるトラックが多い。九州では、鳥栖や北九州に物流の拠点があって、そこから九州全体をデリバリーしている。北九州を通りたいとなると、その分の目減りがある。トラック業者はピークに合わせてトラックの台数を持っているわけではなく、ピストンで、空でも帰らなければならない。上下便のバランスをどうしていくのか、頭を悩ませている。下りの貨物需要を喚起したいということで協議会をつくり、県からの支援を受けてセールスをしている。ただ、大きな流れになっておらず、地道にやるしかない」と説明しました。
船員の確保について、郡司社長から「担い手不足は大きな課題だが、宮崎海洋高校がすぐ近くにある。同校の生徒さんには、研修をさせていただいたり、避難訓練のお客さん役を務めていただいたりしている。その中で、乗っていただく方が毎年おられる」とのことでした。
また、郡司社長から「重油価格の高騰がコスト増につながっていて苦慮している。激変緩和措置として国からもご支援いただいている。もし、この措置がなかったら、弊社の経費に占める燃料費は4割になる。なんとか3割以下にしたい」とした上で、「燃料費高騰は経営に直結。産業用重油についても配慮していただくよう、切にお願いしたい」との要望がありました。
さらに、「2024年問題については、しっかりと実効性を担保してほしい。トラックドライバーの時間外労働の上限規制ではあるが、地域の物流を再構築するきっかけになると思う。荷主や消費者の理解をいただきながら、農産物を安定的に消費者に届けられる体制を議論すべき」と述べました。
■きゅうり農家を訪問、施設を視察し、意見交換(宮崎市高岡町)

一行は、宮崎市高岡町できゅうりのハウス栽培を家族で営む農家、重永義明さんを訪問、ハウス内にてきゅうりの栽培状況を視察、概況説明を伺った後、JAみやざき高岡支店にて意見交換を行いました。重永さんはきゅうり栽培を始めてから33年、現在は27aのハウスで3,000株のきゅうりを栽培し、ほかに1haの水稲栽培を行っています。
11月から2月、3月頃まで、ハウスの加温のために重油が必要となりますが、燃油価格、資材価格が上がっており、農家の経営には痛いとのことです。
自らの経営の規模拡大については、「農繁期は家族総出で懐中電灯をつけて夜中まで農作業をしている。規模拡大はもう少し若ければ考えたかもしれないが、家族労働だけでは無理で、パートが必要となるが、人件費なども考えれば、難しいと思う」とのことでした。
後継者について、「JA宮崎の中央地区管内で、きゅうり、ピーマンなど収入が安定している部門では、後継者が確保できている経営もあり、異業種からの新規参入もあるなど、他の地域よりも良い。ただ、10年後20年後には相当減ってくるのではないかと、危機感を持っている」と語りました。
新規就農については、「農業法人に就職する人もいるが、どちらかというと、自営が多い。ただ初期投資がかかるので、後継者がおらず、リタイヤする農家の施設に居抜きで入って同じ作物を作っていこうという若手が多い」「普及センターが、若手に対し、農業を始めたいのであれば貯金700万円が必要、と言っている」との説明がありました。
また、自らの経営の後継者について「息子がやりたいと言えばやらせてもいいが、強制はしない。自分の子供でなくても、やる気がある人がいれば施設を譲り、技術についてもお手伝いし、つなげていく」との考えを示しました。
最後に、田名部隊長から、「国家プロジェクトとしての食料安全保障をどうするのか、皆さんのお知恵をいただき、政策作りに生かしていきたい」と述べました。
野田代表からは「予算の推移をみると、防衛予算は右肩上がり、文部科学予算は横ばい、農林水産予算は右肩下がり。様々な政策が必要であるが、お金の使い方を変えるのが政権交代」と語りました。
メディアの取材に応じた田名部隊長は、「中山間地域の耕作放棄地で放牧をしている繁殖農家の取組を視察した。条件不利地域でもやり方によって発展できる要素がある。こうした取組を生かすため国の支援があれば、これまでとは違った展開があるとのアドバイスをいただいた。どういう支援ができるか、検討したい」と語りました。
■立憲宮崎第3回政治塾「立憲民主党の農業政策」(宮崎市霧島)

一行は、9日午前、宮崎市のJAアズムにて、「立憲民主党の農業政策」をテーマに開催された「立憲民主党第3回政治塾」に参加、渡辺創衆院議員が司会を、田名部匡代隊長と神谷裕衆院議員が講師を務めました。
政治塾は、渡辺創衆院議員が聞き役となり、田名部隊長、神谷衆院議員が、農林水産キャラバンの取組、前日の視察の感想、食料・農業・農村基本法改正から基本計画に至る経緯と立憲民主党の対応、令和の米騒動の状況と対応、立憲民主党の農業政策の方向性などについて語る、鼎談方式の座談会で行われました。
質疑応答の時間では、会場からは、「値段が安くてもスーパーで米は買わず、高くても地元のお米屋さんで買うのが我が家の食料安全保障」「農家は来年1割増産してくれと言われてもすぐにはできない。食料増産のために、耕作放棄地を再度農地化すべき」「農家の所得補償をしっかりと進めてほしい」「若手には新規就農支援策はあるが、定年帰農には支援がほとんどない。定年退職者への就農支援をすべき」「介護施設は人手不足。介護職と農家は準公務員にすべき」「農政の問題を語るとき、消費者の目線は絶対に必要。首都圏出身の議員を巻き込んだ農業政策が必要」「戦時中、戦後の混乱期、食べることに大変苦労した。祖母は米を食べたいと言って死んでいった。私も死ぬときは日本のごはんを食べたい。日本から米をなくさないようにお願いしたい」といった、様々な発言がありました。
会場からのご発言を踏まえ、田名部隊長は「農地を農地としてしっかり維持することが大事で、農地に着目した直接支払いができないか検討している」「消費者目線は大事。都市農業の重要性を含め、意見してくれる仲間がいる。特に、最後の言葉は胸にしみた。素晴らしい食文化を有する日本。どんな状況に追い込まれても米で人を救えるという日本であり続けたいと思っている。いただいた意見を参考に、みんなで、国家プロジェクトとして日本の農業を世界に誇れる農業としていきたい」と述べました。
神谷議員は、「生産者よりもスーパーの方が強い。生産者も消費者もお互いのことを考えて適正価格が実現できるかどうか。こうしたことから、直接支払い、所得補償を考えている」「復田を抑制する政策が行われている。食料供給困難事態対策法には問題がある」「定年帰農への支援が不十分な中、半農半X、関係人口を増やしていくための支援をどうしていくか、鋭意話し合われており、党内外で頑張っていきたい」「食べてもらわなければ、農業は産業として成り立たない。食料・農業・農村基本法に消費者の役割が位置付けられており、改めて、消費者の重要性を確認した。お米は大事。おいしいごはんを食べて笑顔になりたいという思いを持ち帰り、頑張っていきたい」と述べました。
